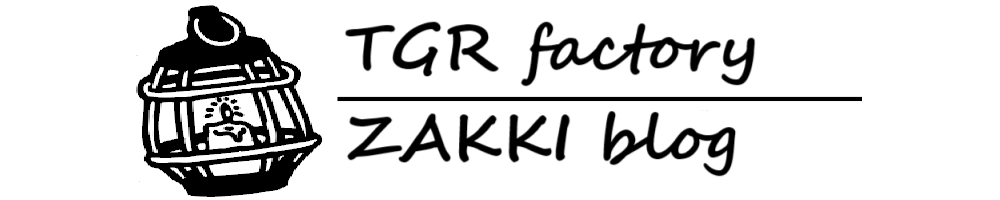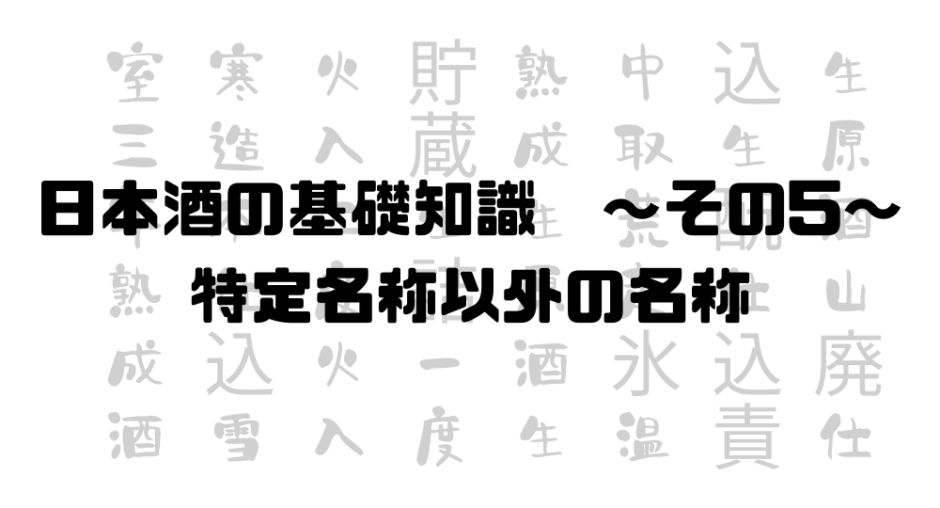この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
当サイトは20歳以上の方を対象としてしております。また、未成年者の飲酒は法律で禁止されています。飲酒に関して、より詳細な情報は厚生労働省の健康日本21(アルコール)や国税庁の20歳未満の者の飲酒防止の推進をご覧ください。
こんにちはTGRです。
今回は日本酒の特定名称以外の名称について説明していこうと思います。
日本酒を眺めていると特定名称の前に「生酛仕込み」や「無濾過生貯蔵」等の妙に長い文言ってよく見ませんか?これっていったいなんなのさ?という疑問にお答えします。

「低温発酵袋吊山廃無濾過生原酒」とか意味わからないですよね。
- 日本酒の特定名称以外の名称の意味
- 名称から推察できる日本酒の味わい
- 酒蔵ごとに考え方が異なる場合がある事
などが分かるはず。
本ページはアフィリエイトプログラムを利用しています。
そもそも日本酒の特定名称、特定名称以外の名称とは
まず、特定名称というのは国が設定した日本酒の区分けの事です。詳しくは「日本酒の基礎知識その1」という記事にしていますので見てみてくださいまし。
 日本酒の基礎知識 ~特定名称~
日本酒の基礎知識 ~特定名称~
まぁ、特定名称は大雑把に言うとアルコール添加の有無と精米歩合によって国の機関が区分したものです。
それ以外の酒蔵独自の製法や火入れのタイミングや回数等を特定名称以外の名称として記載しているんです。

うちの酒は普通の酒とはここが違うんですよ~!っていう蔵元の主張ですね。
ちなみに今回の記事は長いので、気になる名称があったら目次から飛んだ方が良いと思います!
特定名称以外の名称の詳細
では、さっそく特定名称以外の名称を紹介していきますね。
生酛造り
生酛造りとは「きもと」と読み、昔ながらの製法で仕込む酒の事です。自然の中にある乳酸菌を取り込む製法で米と米麹を櫂(かい)というデッキブラシのブラシ部分を取ったような道具ですりつぶす「山卸し」という作業をします。
乳酸菌を添加しないので、仕込みに時間がかかります。
また、昔ながらの製法のため、本来なら乳酸菌が酒の中の雑菌を倒してくれるはずが、逆に雑菌が繁殖してしまい酒を腐らせるリスクがあります。
味わいとしては酸味が際立つ印象です。
生酛(きもと)造りとは、昔ながらの酒造りの方法の事。
- 伝統的な酒造りの方法
- 山卸しという作業を行う
- 乳酸菌の添加はしない
- 仕込みに時間がかかる
- 酒を腐らせるリスクがある
- 酸味が際立つ酒が多い

この酒は伝統的な酒造りをしてますよ!って事ですね。
山廃造り
山廃造りとは「やまはい」と読み、生酛造りの山卸しの作業をしない製法です。山卸しを廃したので「やまはい」。分かりやすいですね。
元々は明治時代に国立醸造研究所の人が

山卸しの作業って無くても酒出来るんじゃないの?ってか調べてみたら山卸ししてもしなくても酒母の成分変わらないよ。
ということを発表し、山卸しの行程を省いた酒造りが広がったという、比較的新しいお酒造りの方法が山廃造りです。
山卸しをしないだけで、ほぼ生酛造りなので味わいも生酛造りに準じたものになります。
山廃造りとは、生酛造りの行程から山卸しという作業を省いたもの。
- ほぼ生酛造り
- 山卸しを廃したから山廃
- 味わいも生酛造りに似る

山卸しはしてないけど、ほぼほぼ伝統的な酒造りをしてますよ~!って事ですね。
寒造り
寒造りとは、冬の寒い時期に造られたお酒の事です。大体12月頃から3月頃に仕込んだお酒。
秋に収穫した新米を使って仕込めたり、冬の寒い時期だと雑菌が少なかったりと美味しい酒造りの理にかなった時期なんです。
また、酵母がアルコールを造り出すときに低い温度で発酵させると雑味の少ない良い味になると言われています。
寒造りとは、冬(12月頃~3月頃)に仕込んだ酒の事。
- 雑菌が少ない時期
- 秋に収穫した新米を使える
- 低温発酵でき、雑味の少ない良い味になる

年中造られてる酒じゃなく、美味しい酒を造れる時期にだけ造られた酒ですよ!っていう事ですね。
低温発酵
低温発酵とは、酒母(もろみ)を低温で発酵させる製法です。低温で発酵させると香りの高い、雑味の少ないフルーティーなお酒になりやすいと言われています。ただ、発酵がゆっくりになるのでその分手間隙がかかるのが欠点と言えます。
反対に温度を高めに発酵させると辛口のお酒になりやすいと言われています。
低温発酵とは、酒母を低温で発酵させる製法です。
- 香り高いフルーティーなお酒になりやすい
- 発酵が遅くなるため時間がかかる

手間隙かけたフルーティーなお酒ですよ~!って事ですね。
無濾過
無濾過とは、絞ったもろみを濾過せずに造られたお酒で、おりや酒粕が若干残る事があります。酒本来の味やフレッシュさが際立ちます。
もろみを絞る段階で、米の固形物等は大体濾される上に、おりは時間がたつと沈殿するので思った以上に綺麗に見えると思います。
昔は無濾過のお酒の品質管理が難しかったようですが、今は管理技術が向上して無濾過のお酒を比較的多く見かけるようになりました。
無濾過とは、搾った酒を濾過しない製法のこと。
- おりがらみになる場合がある
- 酒本来の味を楽しめる
- 近年品質管理技術が上昇し、気軽に楽しめるようになった
- 酒本来の味を楽しめる

酒本来の味を楽しめるし、品質管理技術の高さも示していますね。
原酒
原酒とは、もろみを搾った後に加水しない製法で、大体の日本酒はアルコール度数が20度ぐらいあり、15~16度になるように水を加えます。原酒の場合は水を加えずに次の行程に進みます。
アルコール度数が高いままだったり、濃い味を楽しめたりもしますが、最近は15~16度の原酒も多く見かけるようになりました。発酵コントロール技術の進歩を感じますね。
20度近い原酒を呑んでると、普通の日本酒の味が薄く感じて物足りなくなるのが怖いところです。
原酒とは、もろみを搾った後に水を加えない製法のこと。
- アルコール度数が高く、人によっては呑みにくい場合がある
- 味が濃い
- アルコール度数が通常の場合は呑みやすく濃厚な味わいになりやすい

「原酒」と書いてあったらアルコール度数を確認してみましょう!
生酒(生生)
生酒とは、本来出荷までに2回行うお酒の火入れ作業を行わない事で、新鮮な味わいを楽しむことが出来ます。お酒によっては微炭酸のような舌の上で弾けるような感覚を味わえます。
欠点は味の劣化スピードが早いのと、低温で管理する必要がある事です。
生酒とは、火入れ作業を1回も行ってないお酒のこと。
- 1度も火入れしない
- 新鮮な味を楽しめる
- 要冷蔵
- 味の劣化スピード早め

フレッシュです。冷蔵保存の上、お早めにお召し上がり下さい!って事ですね。
生貯蔵
生貯蔵とは、本来出荷までに2回行うお酒の火入れ作業を瓶詰め前の1回のみ行うことで、生酒のような新鮮な味を楽しむことができます。
生酒ほど品質管理が必要ではありませんが、要冷蔵のお酒が多いです。
また、味の劣化スピードが生酒と比べると緩やかですが、2度火が入っているお酒と比べると劣化スピードが早めです。
生貯蔵とは、お酒の火入れ作業を1回したお酒の事。
- 生酒のような味わい
- 品質管理が生酒より楽
- 2回火が入っているお酒と比べると劣化スピードが早い
- 要冷蔵な酒が多い
- 生酒を貯蔵、出荷前に火入れ

生酒のようにフレッシュだけど、品質管理がそこまでうるさくないですよ~!って事ですね。
生詰(生詰め)
生詰めとは、本来出荷までに2回行うお酒の火入れ作業を貯蔵前の1回のみ行うことで、生酒のような新鮮な味を楽しむことができます。
生酒と比べるとまろやかな味わいになると言われています。
生貯蔵と同じく生酒ほど品質管理が必要ではありませんが、要冷蔵のお酒が多いです。
また、劣化スピードについても生貯蔵と同じく生酒と比べると緩やかですが、2度火が入っているお酒と比べると劣化スピードが早めです。
ちなみに春に仕込んだ酒を生詰で秋に出荷した純米酒を「ひやおろし」と言ったりします。
生詰めとは、お酒の火入れ作業を出荷前に1回したお酒の事。
- 生貯蔵に準ずる
- 生酒よりもまろやかな味わい
- 貯蔵前に火入れ、瓶詰めして出荷

生貯蔵と同じく、1度火入れでフレッシュですよ~!って事ですね。
二度火入れ
二度火入れとは、出荷までに火入れという加熱作業を2回に渡って行うことで、雑菌の繁殖を抑制したり酒の中の酵母や酵素の働きを抑え、味の変化を緩やかにさせ、長期保存や常温保存をする事が出来ます。
フレッシュさに欠ける事が難点なので

生酒の下位互換でしょ~
…と考える人がたまにいますが、酒蔵の人が「美味しい!」と思ったタイミングの酒を長く楽しむことが出来ると考えると、二度火入れには二度火入れの良さがあります。
火入れのタイミングはもろみを絞った後、貯蔵前に1回。出荷時の瓶詰め前に1回の計2回となります。
二度火入れとは、もろみを絞ってから出荷までに2回加熱処理を行うこと。
- 雑菌の繁殖を抑制、殺菌できる
- 酵母、酵素の働きを抑え、味を安定させる
- 長期保存、常温保存が可能
- フレッシュさに欠ける

火入れと言っても、酒自体を煮立たせる訳じゃなく、お湯で湯煎する感じです。
ひやおろし
ひやおろしとは、春に仕込んだ純米酒を生詰めで秋口に出荷したお酒の事で、若干の熟成感があるのが特徴です。
諸説ありますが、元々は品質管理技術が発達していなかった頃、夏場に酒を仕込むと腐ってしまう確率が高かった事から春に仕込んだ酒を火入れして貯蔵し、秋に出荷する事によって一年中日本酒を出荷出来るようにしたことが始まり。っていう説が理にかなってて好きです。
最近は品質管理技術が高くなり、逆に熟成感の無いひやおろしも多く見掛けられるようになりました。
ちなみに「ひやおろし」は純米酒だけに付けることの出来る名称だったと記憶しています。純米吟醸酒や純米大吟醸酒等の他の特定名称酒の場合は「秋あがり」や「秋酒」として販売されていたはず…

ごめん、確証が無いので言いきれません。でも、確かそうだったはず…!
ひやおろしとは、生詰酒の一種で春に仕込んだ酒を秋に出荷した純米酒のこと。
- 生詰めの一種
- 少し熟成感がある(最近はそうでもない)
- 純米酒のみに付けられる名称のはず
- 秋の日本酒

秋を告げる熟成感のある純米酒!って事ですね。
しぼりたて
しぼりたてとは、冬の新酒の生酒のことで、大体ひやおろしの後の時期に出荷されます。
生酒なので弾けるようなフレッシュな味わいが特徴です。
結構蔵元ごとにしぼりたての解釈が違かったりするので、明確な定義はないのかもしれません。
しぼりたてとは、冬の新酒の生酒のこと。
- 生酒の一種
- 秋に収穫した米を使った新酒
- フレッシュな味わい
- 冬の日本酒

冬の到来を感じさせつつ、日本酒造りのシーズンが始まった事を感じさせてくれるお酒!って事ですね。
槽垂れ(ふなだれ)
槽垂れとは、もろみを圧縮して搾る機械から、圧力を掛ける前に自然に落ちてきたお酒を集めたお酒の事で、圧力が掛かっていない分、雑味が少なく繊細で香り豊かなお酒になりやすいと言われています。
もろみを圧縮して搾る機械の事を「槽(ふね)」と言いますが、槽も各蔵元ごとに結構違いがあったりします。形が舟に似ているかららしいですが、そんなに似てるかな?似てない槽しか見たこと無いのかも。なんか四角い桶に棒が付いてるような…
ちなみに槽を使用して圧力を掛けて搾ったお酒を「槽搾り」と言ったりします。近代的な搾り機と比べると、雑味の少ないお酒になります。
槽垂れとは、もろみを搾る方法の一つ。
- 槽から圧力を掛けずに垂れてきた酒
- 雑味が少なく繊細な味

重力のみで搾った手間隙かけた贅沢なお酒!って事ですね。
袋吊り(雫酒)
袋吊りとは、もろみを袋に詰めて吊り下げ、圧力を掛けずに滴り落ちるお酒を集める作業の事で、袋吊りのお酒は手間隙が掛かりますが、雑味が少なく、繊細な味わいになります。高級な酒や品評会に出品するような酒に多く使われています。
ただ、袋吊りの方法については蔵元ごとに異なり、蔵元によっては袋を積み重ねて上から圧力を掛けて搾る方法を袋吊りを言う場合もあります。
袋吊りとは、もろみを搾る方法の一つ。
- 手間隙が掛かる
- 高級酒や品評会出品酒に多く使われる
- 基本は自重で搾る
- 雑味が少なく繊細な味

蔵元ごとにやり方が違うけど、基本的には手間隙かけた高級なお酒ですよ~!って事ですね。
瓶囲い
瓶囲いとは、もろみを搾ったお酒をタンクではなく、瓶に入れ貯蔵したお酒の事で、品質管理が容易であったり味の良いお酒を造りやすいと言われています。
ちなみに18リットルの斗瓶に入れて貯蔵したものを斗瓶囲いと言い、高級酒等に使われることが多いです。
瓶囲いとはもろみを搾ったお酒を瓶で貯蔵する方法
- タンク貯蔵と比べると品質管理が容易
- 斗瓶囲いの場合は高級酒が多い

大きなタンクじゃなくて小分けにして丁寧に貯蔵してますよ~!って事ですね。
荒走り(あらばしり)
荒走りとは、もろみを搾るときに最初に出てくるお酒の事で、あまり圧力が掛かっていないため雑味が少なく瑞々しくとてもフレッシュな味わいになると言われています。
もろみを搾ったときの時間軸で、順番に「荒走り」「中取り」「責め」と呼ばれています。
荒走りとは、もろみを搾るときに最初に出てくるお酒の事。
- あまり圧力が掛かってない
- 槽で搾ってる場合は槽垂れとほぼ同じ
- 雑味が少なく瑞々しくフレッシュな味

搾ったタイミングで名前を変えるほど、特別な酒を仕込んでる!って事ですね。
中取り
中取りとは、もろみを搾るときに中間に出てくるお酒の事で、一番酒質の良いお酒とされていて品評会等に出品されるお酒に使われる事が多くなっています。
中取りとは、もろみを搾るときに荒走りの後に出てくるお酒の事。
- 一番酒質の良いところと言われている
- 品評会に出品したりする酒が多い

搾ったタイミングで名前を変えるほど特別な酒を仕込んでる!って事ですね。
責め
責めとは、もろみを搾るときに最後に出てくるお酒の事で、少し強めに圧力を掛けて搾るため荒々しいワイルドな味になります。
場合によってはアルコール度数が少し高くなる場合もあるようです。
責めとは、もろみを搾るときに中取りの後、最後に出てくるお酒の事。
- 圧力を少し強めに掛ける
- 荒々しいワイルドな味になる
- 雑味が少し混じる

搾ったタイミングで名前を変えるほど特別な酒を仕込んでる!って事ですね。
直汲み
直汲みとは、もろみを搾ったお酒をそのまま瓶に詰める作業の事で、フレッシュな味わいを楽しむことが出来ると言われています。
また、生きた酵母の働きにより微炭酸になる場合があり、舌にピリピリと弾ける感覚が楽しめます。
瓶囲いに似ていますが、瓶囲いは貯蔵方法なので異なります。
直汲みとは、もろみを搾ったお酒をそのまま瓶に詰める事。
- フレッシュな味わい
- 酵母が生きてるので発泡感がある
- 手間隙が掛かる

手間隙かけたフレッシュなお酒って事ですね。
思った以上に沢山あるかも…

思い付いた限り書いてみましたが、どうでしたでしょうか?
知りたかった名称ありましたか?もし無かったらコメント下さいまし。調べて追記させていただきます。
蔵ごとの解釈が難点
今回まとめている時に改めて気付いたんですが、特定名称以外の名称は結構蔵元ごとに解釈が異なる場合があるんだなぁ…としみじみ感じました
特に搾るときの名称なんかは
- 絞り出してから何リットルが荒走り
- 次の何リットルが中取り
- 責めは最後に酒袋に何kgの負荷を掛けて搾った最後の何リットルの名称の事
みたいな細かいルールが無いので蔵元ごとに異なったルールでお酒を造っています。
また、袋吊りと槽垂れと荒走りの線引きが曖昧だったり、袋吊りは自重で搾るのかと思いきや、圧力を掛けて搾っても袋吊りって言う場合もあるし…
それぞれ全く同じではない…それが良い!
まぁ、それぞれの蔵で使っている機材が異なるんだから、それぞれの名称のアプローチ方法も異なってくるのは必然なのかもしれません。
特定名称以外の名称は、あまりあてにし過ぎずに、

蔵元さんが手間隙掛けて造ったお酒なんだなぁ
ぐらいの距離感で良いのかもしれません。
それぞれの蔵元の創意工夫を楽しんで呑めることが一番ですね。
でわでわ。