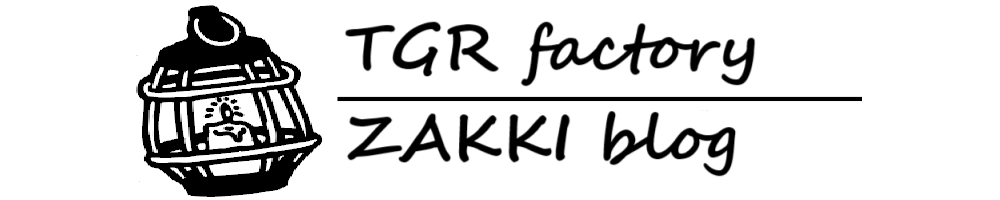この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
当サイトは20歳以上の方を対象としてしております。また、未成年者の飲酒は法律で禁止されています。飲酒に関して、より詳細な情報は厚生労働省の健康日本21(アルコール)や国税庁の20歳未満の者の飲酒防止の推進をご覧ください。
「本当に美味しい日本酒とは何か?」「次世代の酒米は、どのような可能性を秘めているのか?」
これらの問いに、鮮烈な答えを示してくれるのが、神戸・灘の老舗酒蔵「沢の鶴」が世に送り出した「沢の鶴 純米大吟醸 NADA88」です。その名は、88時間かけて精米するという、常識を超えたこだわりに由来します。
しかし、NADA88の物語の核心は、単なる長時間精米ではありません。この至高の一滴は、三百余年の歴史を持つ沢の鶴の伝統的な醸造技術、農業・産業機械で知られるヤンマーの先進的な精米技術、そして何よりも、ヤンマーが開発した革新的な新品種酒米「OR2271」という、三位一体の類稀なるコラボレーションによって生み出されたのです。
この記事では、「沢の鶴 純米大吟醸 NADA88」が、新品種「OR2271」と先進技術によってどのように生まれ、どのような唯一無二の魅力を持つのか、その背景にあるストーリーから味わいの詳細、楽しみ方、購入方法に至るまで、あらゆる角度から徹底的に解剖していきます。日本酒の新たな地平を切り開くNADA88の世界へようこそ。
沢の鶴 純米大吟醸 NADA88 – 革新の酒米と技術の結晶
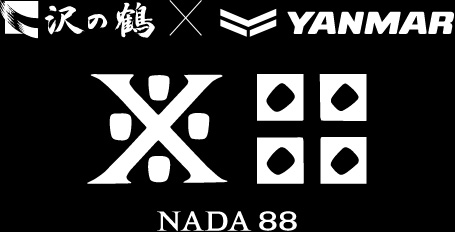
まず、「沢の鶴 純米大吟醸 NADA88」がどのような日本酒なのか、その基本情報から見ていきましょう。この酒の根幹には、ヤンマーが開発した新品種酒米「OR2271」があります。
NADA88は、沢の鶴のラインナップの中でも、未来を見据えた革新性と最高の品質を追求したプレミアムな純米大吟醸酒です。その最大の特徴は、原料米とその精米方法にあります。使用されているのは、従来の有名品種ではなく、ヤンマー株式会社が独自に開発した新品種の酒米「OR2271」です。
この革新的な米を、88時間という驚異的な時間をかけて丁寧に磨き上げていることから「NADA88」と名付けられました。一般的な大吟醸酒の精米時間(40~60時間程度)を遥かに超えるこの時間は、米への負担を最小限に抑え、そのポテンシャルを最大限に引き出すための選択です。
米の外層部にある雑味の原因となる成分を徹底的に除去するため、米を65%も削り取り、中心部の純粋なデンプン質だけを贅沢に使用する精米歩合35%を実現。OR2271の特性と相まって、極めてクリアで洗練された酒質を生み出しています。スペックとしては、特定名称は純米大吟醸酒、原材料は米(国産)と米こうじ(国産米)、使用米はOR2271を100%使用し、アルコール度数は16.0%です。容量は720mlで提供されています。
NADA88の品質は、国内外のコンペティションでも高く評価されており、「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」では複数年にわたり金賞を受賞するなど、プロフェッショナルからも認められています。このように、NADA88は伝統的な酒造りの枠組みに、「新品種酒米の開発」と「先進的な精米技術」という二つの大きな革新を取り入れた、まさに沢の鶴とヤンマーの情熱と挑戦の象徴なのです。
\ご購入はこちらからできますよ!/
沢の鶴×ヤンマー 共同開発ストーリー【新品種開発編】

沢の鶴とヤンマーのコラボレーションは、単に精米技術の協力に留まりませんでした。その核心には、ヤンマーによる新品種酒米「OR2271」の開発があり、これがNADA88プロジェクトの根幹を成しています。
共同開発の背景 – より深い「米」への挑戦
沢の鶴は常に「米を生かす」酒造りを追求する中で、未来の酒造りを見据えた新しい可能性を模索していました。一方、ヤンマーは農業機械メーカーとして、栽培しやすく、かつ食味や加工適性に優れた米品種の開発にも長年取り組んできました。「食の恵みを未来へ」という共通の想いが両社を結びつけ、単に「良い米をどう磨くか」だけでなく、「最高の酒を造るために、どのような米が必要か」という、より根源的な問いから共同開発はスタートしました。
ヤンマーの挑戦 – 新品種酒米「OR2271」の誕生
ヤンマーは長年の米研究と育種技術を結集し、酒米の王様「山田錦」のような優れた酒造適性を持ちながら、栽培面での課題(背が高く倒れやすいなど)を克服する新品種の開発に着手。数多くの交配と選抜を経て「OR2271」を誕生させました。この米は、優れた栽培特性(耐倒伏性、収量性など)と優れた酒造適性(大きな心白、低いタンパク質含有量、高精白への適性など)を兼ね備えています。つまり、生産者と酒蔵双方にとってメリットのある、画期的な新品種なのです。
革新技術「高精度異形精米技術」との連携
そして、このOR2271のポテンシャルを最大限に引き出すために、ヤンマーのもう一つの革新技術「高精度異形精米技術」が活かされました。この技術は米一粒一粒の形状に沿って均一に磨き上げることを可能にし、米へのダメージを最小限に抑えながら雑味成分だけを効率的に除去します。
「88時間精米」へのこだわりと共同開発の意義
新品種OR2271と高精度異形精米技術の組み合わせにより、理論上は精米時間を短縮できたかもしれません。しかし、両社はあえて「88時間」という長時間精米を選択。これには、新品種「OR2271」という「米」への敬意(米=八十八)に加え、時間をかけて丁寧に磨き上げることで米への物理的ストレスや熱の発生を極限まで抑え、OR2271が持つ繊細な香味成分を損なうことなく、そのポテンシャルを最大限に引き出すという、品質への強いこだわりが込められています。
この「新品種OR2271」「高精度異形精米技術」「88時間精米」という三つの要素の組み合わせが、NADA88独自のクリアで軽快な酒質と、ピュアな旨味・甘み、華やかな香りを生み出しているのです。この共同開発は、日本酒業界と農業技術分野における画期的な価値創造のモデルケースであり、伝統産業への技術革新、業界の垣根を超えた価値創造、そして「米」文化への貢献という重要な意義を持っています。
酒蔵「沢の鶴」の流儀 – 三百年の歴史を紡ぐ

NADA88の革新性を支えるのは、揺るぎない沢の鶴の伝統です。三百余年にわたり灘の地で受け継がれてきた酒造りの哲学と技術が、新しい挑戦を可能にする土台となっています。
創業と灘五郷での歩み
1717年(享保2年)創業の沢の鶴は、日本屈指の酒どころ「灘五郷」の西郷に蔵を構え、その歴史を刻んできました。良質な水「宮水」、酒米(かつては山田錦、そして今はOR2271への挑戦)、六甲おろしがもたらす気候、丹波杜氏の技、そして港に近い立地という灘の恵まれた環境の中で、常に時代が求める酒を追求し続けてきました。
「米を生かす」酒造りの哲学と新たな挑戦
沢の鶴の根幹にあるのは「米を生かす」という哲学です。最高の酒のためには最高の米、そしてその米の特性を最大限に引き出す技術が必要という信念。この哲学があったからこそ、ヤンマーと共に新品種「OR2271」の開発と、それを用いた新たな酒造りに挑戦することができたのです。これは、沢の鶴の伝統が常に革新への扉を開いていることの証左と言えます。
水・技術・人 – 沢の鶴のこだわり
仕込み水には灘の酒造りを支える名水「宮水」を使用し、沢の鶴らしいしっかりとした骨格とキレのある味わいの基礎を築いています。技術面では、生酛(きもと)造りのような伝統的な技術を大切に継承する一方、常に最新の醸造理論や設備を取り入れ、品質向上に努めてきました。NADA88におけるヤンマーとの共同開発は、まさにその「伝統と革新の調和」を体現するものです。そして、どんなに優れた米や技術があっても、酒の魂を吹き込むのは人の手。経験豊かな杜氏と蔵人たちが、OR2271という新しいパートナーと向き合い、その声に耳を傾け、五感を研ぎ澄ませて日々の醸造に取り組んでいます。
沢の鶴資料館 – 歴史と未来への架け橋
神戸市灘区にある「沢の鶴資料館」では、灘の酒造りの歴史を学ぶことができます。伝統的な酒蔵の建物や道具に触れることで、沢の鶴が歩んできた道と、その上にNADA88のような未来への挑戦が続いていることを感じられるでしょう。沢の鶴の三百余年の歴史は、単なる過去の遺産ではなく、革新を生み出すための力強い推進力となっているのです。
NADA88の核 – 革新の酒米 OR2271

NADA88の物語の中心にいるのは、間違いなく新品種酒米「OR2271」です。ヤンマーが生み出したこの革新的な米について、さらに詳しく見ていきましょう。
OR2271 – 開発の狙いと背景
ヤンマーがOR2271の開発に着手した背景には、現代の農業と日本酒業界が抱える課題がありました。従来の代表的な酒米「山田錦」は優れた酒造適性を持つ反面、栽培が難しく倒れやすいという課題がありました。ヤンマーは、「栽培しやすく、安定した収量が見込め、かつ高品質な酒造りに適した、新しいタイプの酒米」を目指し、OR2271を開発しました。
OR2271の主な特徴 – 栽培特性と酒造適性
OR2271は、稲の背丈が短く倒れにくい耐倒伏性、安定した収量性といった優れた栽培特性を持っています。同時に、酒造適性にも優れており、酒造りに重要な心白(米の中心部のデンプン質)が大きく、雑味の原因となるタンパク質含有量が低いという特徴があります。さらに、粒質がしっかりしており砕けにくいため、NADA88のような精米歩合35%という高度な精米にも適しています。
NADA88におけるOR2271の役割と可能性
OR2271は、山田錦の芳醇さとは異なる、「クリア」「軽快」「キレが良い」「綺麗な甘み」といった方向性の個性を引き出しやすい可能性を秘めています。沢の鶴がNADA88にこの米を採用したのは、その特性が目指す「究極の純米大吟醸」のコンセプトに合致したからです。ヤンマーの高精度異形精米技術と88時間精米によって、OR2271のポテンシャルは最大限に引き出され、雑味なく、米の中心にあるピュアな旨味と甘み、繊細な香りがクリアに表現されています。OR2271は、NADA88の革新性を象徴し、日本酒の未来を拓く注目の酒米なのです。
NADA88の神髄 – OR2271が生む味わいと香りの世界

革新の酒米「OR2271」を、88時間かけて精米し、沢の鶴の技で醸したNADA88。その味わいと香りは、従来の純米大吟醸とは一線を画す、独自の魅力に満ちています。OR2271の特徴を意識しながら、その官能的な世界を探求します。
テイスティングレビュー
- 外観: 極めて淡く澄み切ったクリスタルクリア。わずかに青みがかったシルバーグリーンを帯び、若々しさと清澄さを感じさせる。中程度の粘性。
- 香り: 驚くほどクリーンで洗練された吟醸香。派手すぎず鮮明に、青リンゴ、洋梨、マスカットのような瑞々しいフルーツ香が立ち上る。繊細な白い花の香りや、微かなハーブのような清涼感も。OR2271由来のピュアさが香りの透明感を際立たせ、従来の山田錦の芳醇さとは異なる、軽やかでシャープな印象。
- 味わい: 口に含んだ瞬間の印象は、極めてスムーズで軽快。清流の水のように広がる。非常にピュアで澄んだ甘みが心地よく、雑味は一切感じられない。綺麗な甘みをキメ細やかで爽やかな酸味が下支えし、味わいに輪郭を与える。旨味は過度に主張せず、軽やかで繊細。苦味や渋味はほぼ皆無。ライトからミディアムライトのボディで、非常に軽快な飲み口。シルクのように滑らかでありながら、シャープな印象も併せ持つ。
- 余韻: 味わいは長く残るというより、潔くすっきりと消えていくキレの良さが際立つ。鼻に抜ける戻り香には繊細なフルーツ香や米の甘い香りが微かに残り、心地よい名残を感じさせる。後味は爽やかでドライな印象すら残し、次の一杯を自然に誘う。
NADA88 の味わいの特徴
OR2271を使用したNADA88は、従来の山田錦ベースの芳醇な純米大吟醸とは異なる、「クリアさ」「軽快さ」「キレの良さ」を特徴とする、新しいスタイルの純米大吟醸と言えます。それは、まるで精密に設計された現代建築のような、無駄がなく洗練された美しさを持つ味わいです。日本酒の新たな可能性を感じさせる、未来志向の味わいと言えるでしょう。
NADA88を最大限に楽しむ – OR2271の個性を引き出す飲用シーンとペアリング

OR2271由来のクリアで軽快な個性を持つNADA88。その魅力を最大限に引き出すには、どのような飲み方、どのような料理と合わせるのが良いのでしょうか。
最適な飲用温度・酒器
NADA88のクリアさを活かすには、やや低めの温度帯、特に5℃~10℃の冷酒がベストです。この温度帯で、爽やかな吟醸香、シャープなキレが最も際立ちます。常温や燗は推奨されません。酒器は、香りを適度に集め、シャープな口当たりを楽しめる小ぶりな白ワイングラスや、クリアな味わいをストレートに舌に届ける薄手のストレートな形状のグラスなどがおすすめです。
極上のマリアージュ – 軽やかさと繊細さを活かすペアリング
NADA88は、素材の味を重視した、軽やかで繊細な料理と素晴らしい相性を見せます。重厚な味わいの料理よりも、シンプルで洗練された料理を選びましょう。味付けはシンプルに、油分は控えめに、香りの強い食材は使いすぎないことがポイントです。繊細な旨味を持つ料理、例えば以下のようなものが考えられます。
- 前菜・アペリティフ: 生牡蠣(レモン・塩)、白身魚のカルパッチョ、野菜スティック、カプレーゼ
- 魚介料理: 淡白な白身魚のお造り(塩・スダチ)、魚介のマリネ、アクアパッツァ、天ぷら(塩で)
- 肉料理(軽め): 蒸し鶏(ネギ塩)、豚しゃぶサラダ(ポン酢)、白身魚のポワレ(軽めのソース)
- その他: フレッシュフルーツ、リコッタチーズ
濃厚なソースやスパイスの強い料理、クセのある食材は、NADA88の繊細な味わいを覆い隠してしまう可能性があるため、避けた方が無難です。
おすすめの飲用シーン
NADA88は、食前酒として、あるいは食事の前半に、軽やかな料理と合わせて楽しむのが最もその真価を発揮するでしょう。特別な記念日の乾杯や、大切なゲストへのおもてなし、あるいは自分へのご褒美など、特別なシーンを彩る一杯としても最適です。
特別な贈り物に – 革新性を伝えるギフトとしてのNADA88

OR2271という新品種を使用したNADA88は、その革新性とストーリー性において、他に類を見ないギフトとしての価値を持っています。美味しさだけでなく、「新しい挑戦」を贈ることができる特別な一本です。
洗練されたデザインと唯一無二のストーリー

まず、シルバーを基調としたボトルと化粧箱の洗練されたデザインが、高級感と共に未来的な印象を与えます。そして何より、そのユニークなストーリーがギフトとしての価値を高めます。
新品種OR2271への挑戦、沢の鶴とヤンマーという異業種コラボレーション、そして88時間精米という品質への情熱。これらの背景は、「なぜこの酒を選んだのか」という贈り手の想いを雄弁に語り、「新しいものが好きな方へ」「技術やものづくりに興味がある方へ」といったメッセージを込めることができます。
品質への信頼とギフトシーン
沢の鶴の確かな醸造技術とヤンマーの先進技術に裏打ちされた品質への信頼も、ギフトとして安心できる点です。クリアで軽快な味わいは、受け取った方に新鮮な驚きと感動を提供するでしょう。
新しい挑戦を始める方へのエールとして、テクノロジーやトレンドに敏感な方への知的な贈り物として、あるいは「他とは違う」特別なギフトを探している場合に、NADA88は最適です。もちろん、父の日やお歳暮、誕生日といった従来のギフトシーンにおいても、そのストーリーを添えることで、より印象深いものになります。
NADA88は、単なる高級酒ではなく、「未来への扉を開く一本」として、記憶に残る特別なギフトとなるはずです。
購入前にチェック!価格、入手方法、口コミ・評判

価格帯と入手方法
NADA88 (180ml) の希望小売価格は2,000円(税込)程度です(2025年4月9日現在)。新品種開発という背景を考慮すると、その価値は価格以上とも言えます。
入手は、沢の鶴公式オンラインショップをはじめ、Amazonや楽天市場などの大手ECサイト、百貨店、日本酒専門店、そして神戸にある沢の鶴資料館ミュージアムショップなどで可能です。購入時には、使用米が「OR2271」であることを確認すると良いでしょう。
口コミ・評判について
これまでの口コミは「華やか」「クリア」「綺麗」といった味わいへの高評価が中心ですが、今後は「OR2271という米を使っていること」への言及が増える可能性があります。「山田錦とは違う軽快さが新しい」「技術の進歩を感じる」といった声が聞かれるかもしれません。「NADA88 OR2271」といったキーワードで検索すると、関連情報が見つかる可能性がありますが、まだ新しい品種のため情報量は限定的かもしれません。
NADA88の購入は、単に美味しいお酒を手に入れるだけでなく、「日本酒の未来」を味わう体験でもあります。その背景にあるストーリーを知ることで、より一層その価値を感じられるでしょう。
もっと美味しく、長く楽しむために – 保存方法と飲み方のヒント

適切な保存方法
NADA88の繊細な品質を保つために、適切な保存が重要です。光(特に紫外線)と高温は大敵ですので、開封前は光を避け、温度変化の少ない冷暗所(理想は冷蔵庫)で立てて保管してください。開封後は必ず冷蔵庫で立てて保管し、そのフレッシュな香味を楽しむためには、できるだけ早く(1週間~2週間程度を目安に)飲み切るのが理想です。
和らぎ水(やわらぎみず)の重要性
美味しい日本酒を楽しむ際には、「和らぎ水」(チェイサー)を用意することを強くおすすめします。水を飲むことで口の中がリフレッシュされ、次の一口を新鮮に感じられるだけでなく、アルコールの吸収を穏やかにし、悪酔いや脱水症状を防ぐ効果があります。NADA88と同量程度の水を交互に飲むのが良いでしょう。
結論:革新の酒米OR2271と技術が生んだ、未来を味わう一杯

「沢の鶴 純米大吟醸 NADA88」は、沢の鶴の三百年の伝統と、ヤンマーの革新的な育種・精米技術が見事に融合して生まれた、まさに「至高の一滴」です。その核心には、ヤンマーが開発した革新的な新品種酒米「OR2271」があります。
88時間かけて丁寧に磨かれたOR2271は、驚くほどクリアで軽快、そして洗練された味わいと香りを生み出し、日本酒の新たな地平を切り開いています。NADA88は、日本酒の新しい可能性を体験したい方、クリアでモダンなスタイルの日本酒が好きな方、技術革新やものづくりのストーリーに魅力を感じる方、そして他にはない知的なギフトを探している方に特におすすめします。
沢の鶴とヤンマーが、米と技術の力で切り開いた未来。その結晶であるNADA88を、ぜひご自身の五感で確かめてみてください。それはきっと、これまでの日本酒のイメージを覆し、新たな感動を与えてくれる、記憶に残る一杯となるはずです。
でわでわ。
▼沢の鶴 純米大吟醸 NADA88 (OR2271使用) のご購入はこちらから▼

\NADA88を覗いてみましょう!/
※本記事の画像は沢の鶴NADA88公式ページより参照